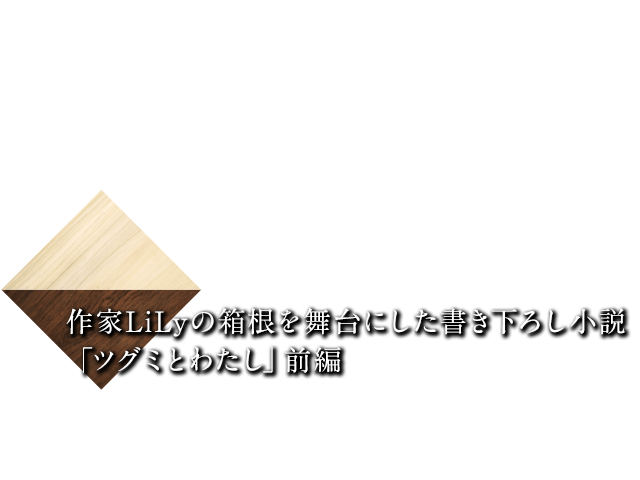
親友というわけではないし、ましてや、恋人でもない。
だけど、気心が知れ、何でも言い合え、どこか気になる男友達——。
女性誌での連載や月9ドラマの脚本協力など、
オトナ女子の心を捉えた描写が人気の作家LiLyが描くのは、
そんな「ツグミ」とわたしが織り成す
“箱根を舞台にした”ラブストーリー。
週末の旅情をくすぐる物語をお楽しみください。
文・LiLy
イラスト・maegamimami
30代は楽しいってみんなは言うけど、え、どこが? としか思えない自分がいる。というか、そもそもそう言っていた「みんな」が誰なのかといえば、メディアに出ている女たち。
いろんな女がいるけれど「彼女たち」に共通しているのは、発言を求められる程度には成功しているということ。
そりゃ、楽しいだろうよ、と鼻白む。
抹茶ラテの甘い湯気が、鼻先を包む。
目の前の優しい香りと、頭の中の苦い声。
待ち時間のヒマを潰すために、ツイッターのタイムラインにあがってきた女性作家のインタビュー記事を読んでしまったせいだ。気分が悪い。
ラテの甘さを濁らせるようなため息を吐きながら、マグカップから視線をあげる。と、
「———もう逃げない、幸せになることから。」
「は? 」
壁に飾られていた洋画のポスターをみて、思わず声が出ていたらしい。右隣に座っている若い女ふたりの視線が、頬のあたりに痛い。込み上げてきたイライラを押し戻すために、舌に熱くて甘い抹茶を喉へと流し込む。
ツグミが待ち合わせ場所に指定した新宿のカフェは、入り組んだ場所にあるのに、週末だからか流行っているのか満席だ。「じゃあ、ここ予約しといたから」と、ツグミがLINEで食べログのリンクを送ってくる店は、いわゆる“オシャレ女子”が好きそうなとこばかり。
淡いグリーンの壁紙を台無しにしている悪趣味なキャッチコピーのポスターを除いては、このカフェもまぁ悪くはなく、例に漏れずに彼らしい。
ツグミは、大学時代からの男友達だ。もう知り合ってから、十年以上が経つ。私たちはともに新聞学科。ツグミは第一志望の出版社に、私はギリギリのところで唯一決まった——名を言っても誰も知らない保険会社に、それぞれ就職した。
在学中からツグミには、隙なく常に、彼女がいる。生まれ育ちも含めて、ずいぶんと恵まれた人間がいたものだ、と彼のことを思っている。それでも仲良くできるのは、異性だから、な気がしている。
彼がもし女だったなら、私はきっと嫉妬をして、他の女友達とおなじようにとっくに疎遠になっている。
けど、どうだろう。
ツグミが入社当初から所属を熱望している少年漫画の部署にまだいけないこと。ほんとうは興味のない女性ファッション誌で編集者として頑張っていること。
そのふたつを支えにして、ツグミと向き合う自分がいる。
完璧にみえなくもない他人の人生だって、そうは上手くいっていないという事実に、癒されるのだ。
いつからだろう、
ネガティブにのみ
救われる。
「遅れた! ごめん! 」と言いながら近づいてくるツグミの息は、切れている。いつも遅れて来るけれど、そのたびにきちんと走ってやってくる。
「ううん、ぜんぜん大丈夫。お疲れさま! 」
目の前の椅子をひいて腰掛けるツグミに、微笑みかける。
仕立ての良い紺色のコートに、黒メガネは今っぽい丸フレーム。
ツグミは年々、垢抜ける。
隣の席の女ふたりに、ツグミのような男と待ち合わせしていた事実を突きつけることができて、私は嬉しい。
「元気? 」
ツグミが白い歯をみせて私に笑う。
「うん、あいかわらずよ、元気だけが取り柄だもん」
明るく、高く弾む、自分の声を冷めた気持ちで聞いている。
ハッピーな楽観主義者は、嫉妬も含めて「全員バカ」だとまとめてくくりあげたりする自分なのに、とても都合のよいことに、私の脳内は他人からは見えない。
「ハハ。ほんと優子は、かわんねぇな」
ね? ツグミもこう言う通り、この三十ニ年間「感じの良い優しい子」としてきちんと社会でやってきている。
コートを脱いで、メニューをめくるツグミのシャツの袖が、真っ白で清潔なことに安心していると、
「安心したよ」
と、ツグミが言う。
「えぇ、なにがぁ?」
赤とピンクの中間の色を指でのせた私の唇がポップにそう話す裏側で、「いやいや、最近ヤバいんだって」ともうひとりの自分が、脳内で低い声を重ねてくる。
目の前のツグミの白い袖が上にあがり、近くの店員を呼び寄せる。ホットのブラックを注文し終えると、ツグミは私に向き合い、少し言いにくそうに「・・・・・・いや、」と言った。
表情を曇らせたツグミに、どちらの自分も共に焦る。ツグミを止めようと顔をあげると、ツグミの後ろの壁から、「———もう逃げない」の文字が目に刺さるように飛んでくる。顔には出さずに私はキレる。「逃げていったのは幸せのほうでしょ、いい加減にしてよ」と、声には出さずに私は怒鳴る。ツグミがこれから続ける内容が、となりの席の女ふたりに聞かれたくないことだと分かっている。が、止まる間もなく、ツグミの唇が動き出す。
「結婚、ダメになってから、実は心配してた」
「やめてよ、そんなむかしのはなしッ!」ツグミの声を消したくて、かぶせるように放ってしまった。トーンの低い、私の声が、店内にヒステリックに響いてしまった。
となりの席の女どころか、店中が一瞬、シンと静まった。ワンテンポ遅れて猛烈に焦った私は、とっさに努めて明るく、はしゃぐようにこの場を取り繕うろうとした。それなのに———、
「••••••ごめん」
ダムが決壊するかのように突然込み上げてきてしまった涙を、どうしても堪えることができなかった。泣くつもりなんて、微塵もなかった。そんなミジメな失態を、私は自分に許せるタイプではまったくない。それなのに、一度流れた涙を、どうしても食い止めることができない。
泣き顔を両手で覆い隠して謝ることだけが、その時の私の精一杯だった。ツグミは頼んだばかりのコーヒーをすぐにキャンセルし、その場で私の抹茶ラテの会計も済ませ、まるで光の速さで私をそこから、連れ出してくれた。

「いつも可愛い彼女がいるの、よくわかった気がする」
いきなり泣いてごめん、ありがとう、を伝える代わりに、ガードレールに寄りかかって缶コーヒーをカチャリとあけるツグミに言った。
「••••••ん? 何故?」
「なんで、じゃなくて、何故って言う人めずらしいよね」
「え? そうかな」
「うん••••••」
人前であんなことになったのは初めてだったのに、不思議と気分は、今までにないくらい晴れていて、私はツグミと、ただ並んで道端に立っている。ツグミはなにも聞いてこないので、私はただ、ツグミが買ってくれた甘いラテの熱い缶を、両手で転がして暖をとっている。
真冬の、カラリとした空の青。
きっと、もう、すぐにでも日が暮れる。ここがオレンジに染まれば、私たちはきっといつもどおり解散し、世界は気づいたら夜になっていて、週末が終わり平日がまたやってくる。
次にツグミに会えるのは、また半年後とか、そんなんだろうか。
男友達というものを彼以外に持たないので平均値を知らないが、連絡だって密にとっているわけじゃない。互いに指一本触れ合ったことなどない関係だけど、それでも、彼女に悪い、という遠慮は常につきまとう。
だから、少しビックリした。
「優子さぁ、これからヒマ? 」
「え、何故?」
「何故、って真似すんなよ」
ツグミが笑って、私も笑う。
「••••••箱根、行かない?」
不意打ちに、思ってもいなかった言葉が降ってきて、一瞬何を言われたのか分からなかった。隣を向くと、ツグミが空をみたまま「行こうよ」とぼんやり言う。
「••••••今、から?」
「そう。ロケハン。つき合ってよ」
なんだ、と肩から力が抜けて、安心するとともにガッカリしている自分に気づく。
「仕事、か」
「そう。LiLyって知ってる? 小説とか書いてる」
ツグミの口から出てきたその名に驚いたのは、ついさっきカフェで彼女のインタビュー記事を読んだばかりだったからだ。私のハッとした顔をみて、ツグミが、「あ、好き?」と少し浮かれた様子で聞いてくる。
ツグミのその、女性誌のエディターっぽい奢った顔にイラッときたからだと思う。
「逆。わりと、けっこう、嫌い」
めずらしく正直に答えた私に、ツグミは目を丸くしてから、ケラケラと笑った。
「いや、さ。箱根に新しく旅館ができるんだけど、そのタイアップで短編小説を頼んでてさ、今。で、一緒見に行く予定だったんだけど、子供が熱出したってさっきメールきてて」
「へぇ、編集者もタイヘンだね。子持ちの女作家と一泊とかするの? 」
「いいや、そんなわけないでしょ、見に行くだけだよ」
どうしてだろう、今までツグミの彼女に嫉妬したことなど一度もないのに、インタビューを読んだ時と同じような感覚で気分が悪かった。メディアの中で粋がる特権めいたものを持つ女に、ツグミまでとられたくないと、すごく思った。
「まぁ、泊まろうと思えば泊まれるんだけど、なんなら泊まる? 写真みただけだけど、めちゃくちゃ素敵な感じだったよ。レンタカーも予約してあるしさ、優子、一緒いかない?」
「••••••明日、仕事あるしな、でも」
泊まる、という言葉に動揺していることを隠したかった。だから、めんどくさそうな声で言いながら、手の中でぬるくなった甘いラテの缶をあけた。
ひとくち飲むと、うっすらと、缶の匂いが喉をとおる。空が、オレンジ色に染まり出す。
ツグミに、いつもみたいに改札で、爽やかにバイバイって手を振れる気はまったくしない。
「行こっかな••••••」
自分の黒いブーツの先を見ながら私が言うと、隣でツグミが「そうだよ、行こうぜ」って、特に嬉しそうでもなんでもなくつぶやき返す。
「日常をリュックにいれて、身体を非日常に運ぶんだって。旅って、そういうことらしい。って、いや、さっきFacebookでまわってきたやつに書いてあっただけだけど」
そう続けて笑ったツグミの横顔は、でもだけど、少しだけ照れているように見えなくもなくて、私は一気に缶の中のラテを飲み干した。
<つづく>

作家。81年神奈川県出身。蠍座。N.Y、フロリダでの海外生活を経て、上智大学卒。最新刊「ここからは、オトナのはなし〜平成の東京、30代の女、結婚と離婚〜」がロングセラーを記録中。現在「オトナミューズ」、「NYLONJapan」、「NUMEROTOKYO」などで連載。
インスタグラム:@LiLyLiLyLiLycom

群馬県出身。女性誌・ウェブ・広告・ブランドとのコラボレーションなどを中心に活動するイラストレーター。また、クッションをはじめとする刺繍作品を展開するアーティスト。女性をモチーフにした作品が主。TBS系連続ドラマ「カルテット」のポスタービジュアルのイラストデザイン及び、主題歌「おとなの掟」(Doughnuts Hole×椎名林檎)のジャケットを制作。初の作品集「maegamimami Grab The Heart」(宝島社)が発売中。

居心地のよい宿は、女子旅に欠かせないもの。こだわり派の女子におすすめしたいのが2017年4月20日にオープン予定の「箱根小涌園 天悠」。箱根の“自然”と“和”のおもてなしをコンセプトにした宿で、非日常感を味わうことができます。絶景の大浴場露天風呂や各部屋に設置されたかけ流し温泉の露天風呂など温泉地ならではのしつらえのほか、スパも併設。ロケーションを生かしたアクティビティなど、ここでしかできない体験ができるのも魅力です。
箱根小涌園 天悠(てんゆう)
住所 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
開業 2017年4月20日
予約 受付中
http://www.ten-yu.com/

※すべての情報は2017年2月27日時点のものです