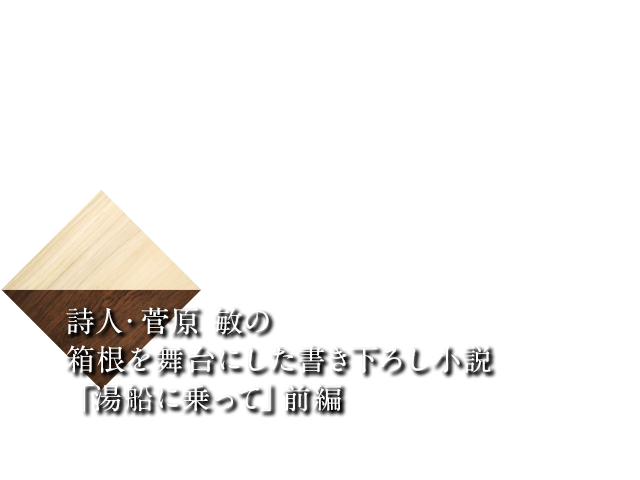
舞台は2028年。
結婚して10年を迎えた二人が向かったのは
かつて一度訪れた、あの箱根の温泉だった。
少し未来の夫婦のかたちとは?
同じ一日で起きた出来事が、
夫からの視点で描かれた前編、
そして妻の視点で描かれる後編。
国内外での朗読公演や、昨年出版された
『かのひと 超訳世界恋愛詩集』でも話題を集める
異色の現代詩人・菅原 敏が描き出す、
せつない夫婦のラブスト―リー。
文・菅原 敏
イラスト・江夏潤一
バックミラーに過去を覗く
私たちは毎年秋に旅に出る。
国内の小さな旅のこともあれば、砂漠の真ん中、銀色の猿が吠える熱帯、
土着品種のワインが美味しい小国、陽の沈まない白夜の国で数週間を過ごしたこともあった。
帰りの飛行機や列車の中で、来年に行く場所の候補を出すようになっていて、今年は長崎県の壱岐、もしくはスリランカに行く予定だった。
妻も私も、見たことのない景色を見たいというタイプだったので同じ旅先に二度訪れたことは一度もない。
妻から10年前に訪れたあの温泉にまた行きたいと言われたとき、思わず「え?」と聞き返してしまった。
確かに素敵な宿だったが、私たち二人にとって、見知らぬ土地を訪れることが通例だったし、
すでに候補は決まっていたからなおのこと意外だった。
今もう一度あの宿を訪れるのも悪くないかもしれない。
10年前、箱根で過ごした日々を思い出していた。
「確かにあそこはよかったね。もう一度行ってみようか」。
2028年の今年、私も妻も38歳になる。結婚したのは2018年、28歳の年だった。
この10年間で私が最も科学の進歩に感謝したことのひとつに車の自動運転がある。
学生の頃に免許を取ったものの、ミラー越しに車間距離を掴む感覚が全く飲み込めず、車線変更の際には形ばかりにミラーを覗き込み、
ウインカーを出すものの後ろから猛スピードの大型トラックにクラクションを鳴らされて、元の車線に戻ろうとすると、今度は観光バスにクラクションを鳴らされる。
本来二車線の道路が、私のせいで三車線になってしまうこともしばしばだった。
結婚当初、妻と初めて二人でドライブしたときにも、休憩に立ち寄った店の駐車場で「これからは私が運転するね」と言われて以降、私が運転する機会はなくなった。
それ以来、私の定位置は助手席となっている。
今では目的地を入力すれば、車内で映画を見ることもできるし、居眠りすることもできる。
走るソファのような手軽さで、私たちは手放しで旅をできるようになったのだが、
今でも時々ガソリン車を自ら運転することにこだわる希少な人たちが事故を起こすたびにニュースになっている。
もはや地球に残っているガソリン車の数は、パンダよりも少ない。
眼鏡の中でメールをチェックして、私はリクライニングシートに体を預け、読書をする妻の横顔を眺めている。
こんな時代でも紙の本を愛する私たちの特徴。海沿いの車窓と妻との間で私は今の幸せを思う。
妻と出会ったばかりの頃、私はひどい恋をひとつ終えたばかりで胸にはぽっかりとドーナツの穴が空いており、帽子を当てれば風に飛ばされてしまうほどだった。
車の心地よい揺れの中で、今ではすっかり朧げになってしまった、昔の恋の記憶を辿ってみる。もはやその終わりしか思い出せないが、今では胸が痛むことはなくなった。
麦わら帽子を胸に当てて、私は穏やかに過去を覗き込む。
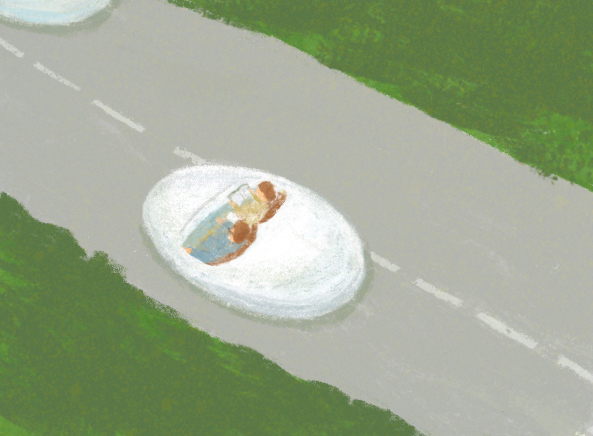
食卓に流れる川
妻と出会う前の8年間、Aという女性と付き合っていた。
恋の始まりの記憶はあやふやだが、終わり際のことは今でもよく覚えている。
私のマンションに転がり込んでくる形で始まった同棲生活だったが、だんだんとすれ違いも増え、
二人の間に流れていた小川は徐々に水かさを増して一級河川のようになっていた。
二人で暮らすことの難しさをまざまざと見せつけられながら、私は当時の様子をこんな風に日記に書き留めていた。
食卓のテーブルを囲む人数は
次第に減ってゆくもので
人を乗せないキリンのように
立ち尽くしている椅子
わずか1mにも満たないテーブル幅
その中央には大きな川が流れ
向こう岸へ声は届かず
もはや泳ぎ切ることもできない
川の流れを指でなぞり
きらきら反射する水面に目をこらし
アフリカからやってきた
珈琲豆を砕いたら
コップひとつが食卓の朝
「食卓に溺れる」
「食卓に珈琲の匂い流れ」という茨城のり子さんの詩がある。
ふと我が暮らしを振り返ると、珈琲の匂いではなく巨大な川が食卓のど真ん中を流れていて、
向こう岸に塩も胡椒も渡すことができず、気づけば向かいの椅子には誰もいない。
時折、皿からこぼしたベーコンの切れっ端などを川の魚たちに分けてやると朝の水面(みなも)をぴちぴち跳ねていた。
二人の距離がもう元に戻ることはないと思い、私はAに別れようと告げた。
Aは引越しのためのお金を貯めるので、半年ほど待って欲しいと言った。
新生活に必要な金額は出すからと言ったものの「そんなサポートは受けない」と頑なにAは拒み、結局私はそれを受け入れた。
半年の猶予期間は残すところ一ヶ月となり、私はすでに引っ越し先を決めていた。
Aに「ちゃんと部屋を探してる?」と聞いても、それとなく受け流し、はっきりと答えることはなかった。
「それより今夜は何食べたい? 青椒肉絲の春巻きにする?」と、どことなくこのままの生活を続けていけると踏んでいるような、小さな強さを感じていた。
ある朝、食卓の上に手帳を開いたままで彼女は洗面所へ。
ふと今日のスケジュールを見ると、都内のホテルの名前が記されていた。今日は実家に帰ると言っていたはずだ。
「いってきます、じゃあ明後日にね」と仕事へと向かったA。
「さて、どうしたものか」と私は食卓に座り、パンくずを指で弾き、すいすいと泳ぐ魚の姿をぼーっと見ていた。
全くしんどいことではあるが、この長い生活の一つの句読点になるだろう。
日もとっぷり暮れた21時に私は彼女の同僚のふりをしてホテルのフロントに電話をかけ「急用なので繋いでください」と内線を回してもらった。
電話の向こうでAは「なんで? どうして? 違うの!」とテンヤワンヤで、何やら男と言い合っている。
「とりあえず今からホテルに行くから」と私は告げて、電話を切った。
タクシーに乗り込んで見た首都高からの景色と、小指が痛くなる革靴を履いていたことをなぜか鮮明に覚えているのだが、
部屋をノックしてからの出来事はあまり現実味がなく映画を見ているかのように過ぎていった。
泣きながら床に座り込んでいるAと、平謝りで慌てふためく彼女の上司。
私はさして感情的になることもなく、二人の姿を見届けるだけでどこかしら満足して、帰っていった。
そして引越しの当日、Aは3つのダンボールを残したまま姿を消してしまい、それ以降会うことはなかった。
電子レンジで体を溶かし
錠剤ばかりのスープをすくい
ほら むせこむばかり愛なんて
二日酔いの頭を撫でて愛なんて
すり減った靴のかかと愛なんて
言葉が膝を撃ち抜いて愛なんて
もはや誰もがあきらめた
地球で最も楽な暮らしを
求め求めて ずぶ濡れの
うそつき抱いて 食卓へ
「キッチン」
柿色の生活
新たに引っ越した町には大きな蓮池があった。縄文時代、この辺り一帯は海だったらしく、この池もかつては海の一部だったそうだ。
海を知らないボートたちが何艘も浮かび、恋人たちは鴨と一緒に池に浮かんでいる。
私は築70年の町屋を気持ちばかり手入れした一軒家に引っ越したのだが、数ヶ月の間は何もすることが出来ず、池の周りを歩き、
近所の店を一軒ずつ回ってはお酒ばかりの日々だった。
真夜中に池のほとりを歩いていると、動物園からは何かの鳴き声がいつも聞こえた。鳥のような気もするし、大きな獣のような気もする。
時折私の家の屋根の上を何かの小動物が駆け抜けるのだが、ついつい動物園を抜け出して来た南米の動物などを想像してしまう。
「ナマケモノはここに住んでいますよ」と、布団に横たわりながら天井の向こうに話かけるのだった。
そんな暮らしの中、いまだ食卓には大きな川が流れていたが、そこに少しずつ橋をかけてくれたのが今の妻だった。
仕事柄、家にこもりがちでほとんど旅に出てこなかった私を色々な場所へと連れていってくれた。
普段は多くを語らない彼女だったが、新たな景色を見にゆくこと、異なる文化に触れることにかけては積極的だった。
家を離れてたくさんの旅しているうちに、食卓の川には少しずつ橋が架けられ、川の流れは穏やかになり、私の胸のドーナツの穴も塞がれていた。
私がふざけて「二人で一生バカンスだね」と言った時、しばらく私を見て「今の言葉、忘れないでね」と言った。
いつもはとても控えめだが、芯の強さを感じることも多かった。
ある秋の夜、私たちは白ワインと一緒に幾つかの果物を食べていた。
私は「柿って苦手だなあ」と言うと、彼女は「私は好き」と言った。
「私は柿くらいでいいの。そんなに人気はないけど、好きな人には好かれて、自分の色を持ってて、渋味もあるし。柿のスタンス、好き」。
彼女のルーツは大陸にあり、時折その表情に異なる歴史の積み重ねを垣間見たりする。
アーモンド形のくっきりとした目、白くてすべやかな肌、ふわふわのおでこ。
私のキッチンにはこれまで知らなかったハーブや調味料が増え、冷蔵庫も新たに迎える食材たちに胸を躍らせて過ごしていた。
気づけば食卓から川の流れは消えて、肥沃な草原になって、窓からの風に緑の波をたなびかせている。私たちは草原に横になり、草の香りの中で眠った。
絆が深まっていくほどに、私は怖かった。
ダンボール3つほどの思い出を残して、食卓に流れる川にドボンと飛び込んだA。あんな日々はもう二度とごめんだ。
柿色の彼女とのこれからを大切にしたかった。段々とすり減っていく、靴のかかとのような日々にはしたくなかった。
私たちは付き合って半年ほどで結婚し、二年ほど経った日から、薬を飲み始めた。
過去と未来をつなぐ乗り物
うとうと眠る私たちを乗せて、車は静かに天悠の敷地に滑り込んだ。
10年ぶりだというのに、足を踏み入れた瞬間から懐かしくよみがえってくる当時の記憶。
丁寧に設えられた室内、露天風呂からの景色、心地の良い接客。誰にも教えたくないような秘密の場所が、今もそこに変わらずあることが嬉しかった。
妻に至っては、まるで初めて訪れたかのように笑顔で目を輝かせている。
夕食までの間、私たちは部屋でくつろぐことにした。16時になり、そろそろ薬を飲もうかとカバンを探った。
いつも必ずそこに入れている内側のポケットに、薬がない。
家を出る前に確かに入れたはずだ。
私は不安に駆られて部屋中をウロウロと探し回り、車の中もチェックし、全てのポケットを探ったがどこにも見つからなかった。
妻にカバンに入れたはずの薬がないことを伝えると、彼女はさして驚きもせず「まあ、一日くらい無くたっていいじゃない」と景色を眺めた。
せっかくの温泉に来たのに薬がないんじゃどうしようもないと私はイライラしながら、妻が入れてくれたお茶をすする。
なぜ妻は薬がないと知っても平常心で居られるのだろうか。
「ほら、夕暮れを楽しみながら露天に入ろうよ。部屋にある露天って、どうしてこんなに嬉しいのかしら」
するりと服をベッドに脱ぎ捨てて、信楽焼の温泉露天風呂に体を滑り込ませた。
私も渋々と服を脱ぎ、妻の向かいにゆっくりと体を沈める。例えようのない開放感が呻きになって溢れる。
妻も微笑みながら浴槽の縁にもたれ、紅葉が始まったばかりの箱根の山々と風を泳ぐトンボたちをゆっくりと眺めている。
なぜだろうか、こうして湯船に浸かっていると過去がほどけて時間が巻き戻っていく。
すっかり忘れていた、Aと出会った頃のことや、もっともっと昔の幾つかの恋たちが不意に思い出されてくる。
そして私は妻の横顔を見る。
ふと目があって「なあに」と笑う。
二人とも少々歳をとったものの、あの日と変わらない気持ちでこのお湯に浸かり、変わらぬ山々の景色を眺めている。
気づけば湯船はゆっくりと岸を離れて、歳月の水面へと静かに漕ぎ出していた。
10年という月日が経っても、薬がなくとも、私は妻にふれ、これからも続く幸せを肌で感じることができる。
10年後、20年後にも、私はこの気持ちで彼女の横顔を見るのだろう。
何も心配することはなかったのかもしれない。
私の過去にぶら下がっていた3つのダンボールは正しい宛先に送られていった。
きっと何年経っても、この場所は変わらぬ笑顔で私たちを迎えてくれるだろう。
もしかしたら、もう薬は必要ないのかもしれない。
湯船は過去と未来を行き来する船のような乗り物。
ずっと古くからこの場所で、時間の狭間でゆらゆらと人を運んできた。
揺れる水面にはこれまでとこれからの私たちが映っている。
私は妻の肩を抱き「さてビールでも飲もうか」と船を降りて、二人で浴衣に袖を通した。
<つづく>

すがわら・びん。詩人。2011年、アメリカの出版社PRE/POSTより詩集『裸でベランダ/ウサギと女たち』で逆輸入デビュー。執筆活動を軸に、異業種とのコラボレーション、ラジオやテレビでの朗読、デパートの館内放送ジャック、ヨーロッパやロシアでの海外公演など広く詩を表現。 Superflyへの歌詞提供、東京藝術大学大学院との共同プロジェクト、美術家とのインスタレーションなど、音楽や美術との接点も多い。 現在は雑誌「BRUTUS」他で連載。2017年7月に新詩集『かのひと 超訳世界恋愛詩集』(東京新聞)を上梓。
Twitter https://twitter.com/sugawara_bin/
インスタグラム https://www.instagram.com/sugawarabin/

こうか・じゅんいち。イラストレーター、アーティスト。1979年、鹿児島生まれ。鹿児島在住。&Premium、FIne、リンネル、山と渓谷など雑誌の仕事を中心に、冊子や広告、ツアーグッズやWEB、雑貨へのイラストなど、さまざまなジャンルで活躍中。
インスタグラム https://www.instagram.com/kokajunichi/
ホームページ http://junichikoka.com

物語の舞台となった箱根の宿は、2017年4月20日に開業した「箱根小涌園 天悠」。
箱根の“自然”と“和”のおもてなしをコンセプトにした宿で、非日常感を味わうことができます。絶景の大浴場露天風呂や各部屋に設置されたかけ流し温泉の露天風呂など温泉地ならではのしつらえのほか、スパも併設。箱根の旅を助けるコンシェルジュが応対する、丁寧な接客も魅力です。
箱根小涌園 天悠(てんゆう)
住所 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
http://www.ten-yu.com/

※すべての情報は2018年9月1日時点のものです